東西四連(東西四大学合唱演奏会)は特別な演奏会です。コンクールのように順位がつくわけではありませんが、日本の東西を代表する関西学院グリークラブ・同志社グリークラブ・早稲田大学グリークラブ・慶應ワグネルの各校が同じステージに立つということは、否応無しに「日本一の合唱団だと認めてもらいたい」という気持ちがつのります。今、自分達が持ち合わせている最高の演奏を残したい。まして最高学年の四年の年であればその思いは尚更でした。
私達が大学四年のときの第36回東西四連(1987年)の曲目は、実は前年度のかなり前の頃から「ブラームスの”Liebeslieder”らしい」という噂が聞こえていました。木下保先生がお亡くなりになり畑中良輔先生が四連を振るようになった後の四年間は、全てドイツ語の曲が選ばれていました。団員の中でも、四連はワグネルの十八番のドイツ語で勝負するのが当然というような雰囲気すらありました。しかも当時、6年前の畑中先生指揮による”Liebeslieder”の名演奏の録音が団員の中で出回っていて、おそらく”Liebeslieder”は歌いたい憧れの曲の筆頭格になっていました。私も、畑中先生の指揮で”Liebeslieder”を歌う機会が来るのを本当に待ち焦がれていたのです。
ところが、前年度の定期演奏会が終わり、新年度が始まってまもなくのこと、畑中先生が次の四連の曲目に「月光とピエロ」を選んだという話を聞かされました。耳を疑いました。「なんで?”Liebeslieder”じゃなかったのか?」「先日(1986年10月)亡くなった清水脩先生の追悼をしようということになったらしい」「そんな…」確かに清水脩先生の功績は認めるものの、”Liebeslieder”と「月光とピエロ」を比べると、まるで四連の格が一段下がってしまうような気さえしました。畑中先生の”Liebeslieder”に憧れていただけに、余計に畑中先生の選曲を恨む気持ちが募りました。正直なところ「最高学年の四連で『月光とピエロ』を歌うためにワグネルに入団したのではない」とすら思ってしまいました。
ただ、畑中先生の練習を迎えると、先生が表現しようとする「月光とピエロ」は、今までに聴いた他の先生方の演奏とは全く違っており、きわめてメッセージ性の強いものであることが分かりました。「現代社会で生きていく君達は皆ピエロなのだ!」。終曲の「ピエロピエレット」を「機械的に、非人間的にリズムを刻んで!」怒涛のように激しいピエロ。畑中先生の表現に心を揺さぶられ、充実した練習のときは過ぎていきました。
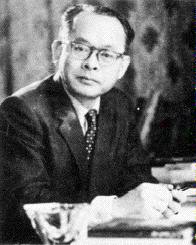
畑中先生の目指していたものをご理解いただくために、パンフレットに載った畑中先生のメッセージの全文を転載します。
「清水先生とわたしとワグネル」
音楽家としての私の出発点に、いつも清水脩先生がいた。昭和25年、第1回の独唱会には清水先生の「在りし日の歌」全5曲を歌った。特に〝サーカス〟が、「畑中君、こんなにペーソスとユーモアを混ぜ合わせて歌った人はいなかった。これこそ中也の詩の真髄というべきだね」とお誉めの言葉をいただいたのも昨日のことのようだ。ワグネル専任指揮者としての第1回目の演奏(昭・35)も、委嘱作品の「朔太郎の三つの詩」の初演である。昭和21年、中支より復員してはじめてのNHK放送も清水先生の「抒情小曲集」を歌った。戦後の苦しい生活に喘いでいた私にNHKの合唱団の仕事はどうかと、当時のNHKの音楽部長のところまで連れていって下さったのも清水先生だった。ワグネル就任の2年後、昭和37年に「月光とピエロ」をとり上げた。翌年は「オーヴェルニュの歌」5曲の編曲委嘱を御願いした。次年は学指揮が「山に祈る」、更に翌年は北村協一君が「アイヌのウポポ」翌40年には私が「智恵子抄」より「巻末のうた六首」に加えて「在る夜のこころ」を委嘱作品として初演した。41年は木下先生の「若者の歌」と続いている。其後ワグネルとしては「日本の祭」「鎮魂曲」の大曲も初演させていただいたりして、ワグネルと清水先生との連帯は大きく、その音楽に対する心構えもなみなみならね気魄があったものだ。
先生が亡くなられて、特に男声合唱界に大きな穴があいたような気がする。今回の「四連」という場を借りて、25年前のワグネルの「月ピエ」を再現したい。それはこの四半世紀に私が内なる世界に培った、あの時とはまた違った「月ピエ」になるだろう。この管理社会・機構の中の、群集の1人としての〝かなしみ〟は、〝いま〟という時を生きる人たちの心の中にみんな屈折している筈だ。嬉しくても笑えず、悲しくても泣けない〈いま〉。ピエロこそ私たちではないのか。装った白塗りの笑いの中から凍った涙が流れおちる。
この重層的構造を音楽の上に明らかにして、いま、この演奏を清水先生に捧げたい。「畑中君、こんなにユーモアとペーソスをパトスの中にくるんだ人はいなかった。これこそ清水脩の真髄というべきだね」と云われるように。
合掌
そして迎えた本番、そこにピエロの落とし穴が待っていたのです。
第36回東西四連(1987年)の会場は前年に開場したサントリーホールでした。
4曲目までは無事に演奏が進んでいきました。最後の5曲目。畑中先生は曲間での音取りを好まれないので、音取り無しで始めます。そのとき、最初の「Lo-」のBASSの音が、なぜか分からなくなってしまったのです。練習の際に音が取れなかったことは一度もありません。それがなぜ、よりによって本番で、突然分からなくなってしまうとは。畑中先生の棒が振り下ろされたとき、ようやく絞り出した声は弱々しく、あいまいな音になってしまいました。そのとき、忘れもしません。たしかに畑中先生と私の目が合いました。「どうした!?」と目が言っていました。選曲を恨めしく思った気持ちがどこかに残っていて、それが落とし穴となって、パックリと口を開けていたのでしょうか。
後から聞いた話では、私達の16年前にピエロが取り上げられたとき、先生がお怒りになって練習中に帰ってしまわれたことがあったのですが、そのきっかけも5曲目の「Lo-」のBASSの音が取れなかったことだったそうです。「なぜか分からないけど、突然音が分からなくなってしまったんだよ」と、先輩が仰るのを聞いて、同じ落とし穴があったのだと不思議に思うのです。
